有田の‘裏通り’を歩く
本年の秋の陶磁器まつりも一昨日で終わり、その期間中ココ有田駅の観光案内所にも多くの皆様方においで頂き、本当にありがとうございました。一時的な混雑やらで十分なご案内が出来なかったんじゃないかと反省もしておりますが、今後の課題とさせて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、“根性松”という言葉は、どうも各地にあるようですネ。“根性の松”とか“ど根性松”とか、いろんな呼び方がされてるようです。いずれも、岩や石の上とか、ごく狭い場所に根付き、よくまァ~こんな所にこんなにしっかりした松が!!といったニュアンスがあるように思いますが・・・いかがでしょうか?(・・実はそうじゃない、“根性松”の定義はこうだ、というのがもしあれば、お教え頂ければ幸甚です・・・笑)
と、いうわけで・・・、遠くから煙突の上に見えていた次のような光景・・・これはまさしく “有田の根性松” と云えるかも知れませんネ。

[有田の‘根性松’!?・・・既に‘市民権’を得ています]
数年前になりますか、小学生の団体の方をご案内してココを通ったとき、これを見つけた小学生の一人が指差して「あっ、根性松だ!!」と叫んだのを聞いたとき、
‘えっ、あヽ、何とピッタシ’と、予想もしなかった言葉に私は妙に感心もし、それ以降その言葉を何かと愛用させても頂いているわけで・・(笑)、‘あヽ、ひょっとすると、あれは、<虹の松原>を擁する唐津の小学生だったから、自然に出た表現だったのかなァ~等と時々思ったりもしてますが・・・(笑)。
実はこういった煙突の上に草木が根付いている光景は有田では時折り見かけます。明治以降、石炭窯等のために数多く建てられていた高い煙突のある風景は、石油(重油)、ガス、そして電気窯への移行や、或いは会社の統廃合等の過程で使われなくなったりと理由は様々かと思いますが、でも、何といっても、この煙突が残っているか否かでは町の風情への貢献度はまったく異なるように思います。遠くからでも、“あヽ、焼き物の街だなァ~”としみじみ感じられる貴重な遺産だと思いますネ。
・・・と、いうわけで、随分前置きが長くなりましたが(笑)、ここの場所にある老舗の会社が 『イワオジキ』 という会社で、この工場は大正初期に建造され、もちろん伝統的建造物に指定されています。

[いかにも大正期の、この風情]
そして、大正ロマンを感じさせるこの旧い風情の工場から、次のような何ともモダンなレリーフ作品を生み出しているという、そのギャップ・・・。ここに私は有田のダイナミックさをみる気がします。

[同社の案内パンフより]
さてそこから、さらに西方へ歩いて行きますと、何やら長い土塀と門構えをもった古いお屋敷が見えてきます。

[トンバイ塀とベンチ。何だか・・・ホッとする情景]

そうです。実はこのお屋敷こそ、日本で初めて宮中へ磁器を納められたという歴史を持つ、 『辻精磁社』 という窯元です。江戸時代初め1660年代のことです。
すなわち、天皇が御使用になられた国産磁器の第一号が、この窯元で作られたものだということですが、さらに時代が下った明治以降、日本で初めての磁器の洋食器を製作されたのもまた、この窯元だと云われています。

門構えを持つトンバイ塀としてとっても情趣があり、焼き物の街有田を飾る観光スポットとして、常にグラビア等に紹介されたり、映画やドラマのロケ地等になったりもしてますョ。
山ちゃんズ、山口♂ でした。
でした。
[N.23]
さて、“根性松”という言葉は、どうも各地にあるようですネ。“根性の松”とか“ど根性松”とか、いろんな呼び方がされてるようです。いずれも、岩や石の上とか、ごく狭い場所に根付き、よくまァ~こんな所にこんなにしっかりした松が!!といったニュアンスがあるように思いますが・・・いかがでしょうか?(・・実はそうじゃない、“根性松”の定義はこうだ、というのがもしあれば、お教え頂ければ幸甚です・・・笑)
と、いうわけで・・・、遠くから煙突の上に見えていた次のような光景・・・これはまさしく “有田の根性松” と云えるかも知れませんネ。

[有田の‘根性松’!?・・・既に‘市民権’を得ています]
数年前になりますか、小学生の団体の方をご案内してココを通ったとき、これを見つけた小学生の一人が指差して「あっ、根性松だ!!」と叫んだのを聞いたとき、
‘えっ、あヽ、何とピッタシ’と、予想もしなかった言葉に私は妙に感心もし、それ以降その言葉を何かと愛用させても頂いているわけで・・(笑)、‘あヽ、ひょっとすると、あれは、<虹の松原>を擁する唐津の小学生だったから、自然に出た表現だったのかなァ~等と時々思ったりもしてますが・・・(笑)。
実はこういった煙突の上に草木が根付いている光景は有田では時折り見かけます。明治以降、石炭窯等のために数多く建てられていた高い煙突のある風景は、石油(重油)、ガス、そして電気窯への移行や、或いは会社の統廃合等の過程で使われなくなったりと理由は様々かと思いますが、でも、何といっても、この煙突が残っているか否かでは町の風情への貢献度はまったく異なるように思います。遠くからでも、“あヽ、焼き物の街だなァ~”としみじみ感じられる貴重な遺産だと思いますネ。
・・・と、いうわけで、随分前置きが長くなりましたが(笑)、ここの場所にある老舗の会社が 『イワオジキ』 という会社で、この工場は大正初期に建造され、もちろん伝統的建造物に指定されています。

[いかにも大正期の、この風情]
そして、大正ロマンを感じさせるこの旧い風情の工場から、次のような何ともモダンなレリーフ作品を生み出しているという、そのギャップ・・・。ここに私は有田のダイナミックさをみる気がします。

[同社の案内パンフより]
さてそこから、さらに西方へ歩いて行きますと、何やら長い土塀と門構えをもった古いお屋敷が見えてきます。

[トンバイ塀とベンチ。何だか・・・ホッとする情景]

そうです。実はこのお屋敷こそ、日本で初めて宮中へ磁器を納められたという歴史を持つ、 『辻精磁社』 という窯元です。江戸時代初め1660年代のことです。
すなわち、天皇が御使用になられた国産磁器の第一号が、この窯元で作られたものだということですが、さらに時代が下った明治以降、日本で初めての磁器の洋食器を製作されたのもまた、この窯元だと云われています。

門構えを持つトンバイ塀としてとっても情趣があり、焼き物の街有田を飾る観光スポットとして、常にグラビア等に紹介されたり、映画やドラマのロケ地等になったりもしてますョ。
山ちゃんズ、山口♂
 でした。
でした。[N.23]


















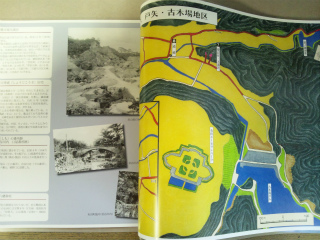



 すごく楽しみにしています
すごく楽しみにしています







 でした。11/9撮影
でした。11/9撮影 




